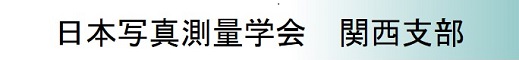2025年度特別講演会・第130回テクニカルセミナー/空間情報話題交換会の報告
2025年7月4日(金)、大阪公立大学 I-siteなんば に於いて2025年度特別講演会・第130回テクニカルセミナー/空間情報話題交換会を開催しました。
|
『全国の標高成果の改定』
国土地理院 近畿地方測量部 田中 宏明 様
講演資料:講演終了一年後に掲載予定
『リモートセンシングから辿り着いた里山工学』
高知工科大学 高木 方隆 様
講演資料:講演終了一年後に掲載予定
|

|
2025年度特別講演会(第130回空間情報話題交換会)では、国土地理院の田中宏明様と高知工科大学の高木方隆様にご講演いただきました。
前半は、田中様より『全国の標高成果の改定』と題して、衛星測位を基盤とする標高の仕組みに移行するための、全国の標高成果の改定についてお話しいただきました。
初めに、標高改定の背景として、近年の地震災害や人為的理由による地盤変動の状況、および既存の標高決定の仕組みである水準測量について紹介があり、これまでの標高体系が抱えていた時間・費用・利便性の問題が説明されました。
次に、衛星測位を基盤とする標高の基準となる重力ジオイド(ジオイド2024 日本とその周辺)の説明がありました。水準測量による標高を用いた実測ジオイドを使用するのではなく、航空重力測量により重力データを高精度に計測し、その結果から計算した重力ジオイドを使用することで、水準測量の誤差なく、かつ地殻変動が生じても安定した基準を得ることができる点を解説いただきました。
最後に、全国の標高成果の改定量と、これからの標高計測について説明がありました。測量成果が改定された現在は、地震等で測量成果が停止された場合も、電子基準点成果が改定されるタイミングで楕円体高とともに標高データが利用可能になることや、3級水準測量に適用可能なGNSS標高測量に関してご説明いただきました。
後半は、高木様より『リモートセンシングから辿り着いた里山工学』と題して、リモートセンシングに関する研究内容と、持続可能な暮らしを支える里山工学についてお話しいただきました。
初めに、リモートセンシングの専門家として携わられた研究や計測を紹介いただきました。今後のリモートセンシング研究の展望として、膨大なデータやAIが活用できる中で、研究者が積み上げる検証用データが重要になることや、リモートセンシング・GISの研究者は、異なる分野の研究をつなぐ役割があることを強調されました。
次に、里山工学の立ち上げの経緯とその体系について説明いただきました。日本の農業の持続可能性や、流域における土地利用の変化に関する問題意識を紹介いただくとともに、生物多様性に配慮しながら自然に手を加え、人間の暮らしを支える里山づくりを実現するために、新しい科学的知見を得ながら既存の技術を再構築する学問としての里山工学を解説いただきました。特に、基盤となる科学技術として、地域の伝承を科学的に立証することや、歴史民族学の観点から過去の土地利用を推測することを説明いただき、それらをもとにした社会実装と具体の成果についても紹介いただきました。さらに、大学での課題解決型学習(PBL)の活動や、地域の市民研究者とのコラボレーションの実践についても紹介いただきました。
最後に、先生が自ら実践されている里山暮らしについて紹介があり、幅広い世代や他の生物にとっても場所となる里山を、暮らしの中で維持されていることを説明いただきました。
ご講演いただきました田中様と高木様にはこの場を借りてお礼申し上げます。
|
※測量系CPD協議会において認定された学習プログラムとして終了後に参加者へ受講書が配布されました。
※GIS上級技術者の認定を受ける際の貢献達成度ポイントとして申請できる参加証も配布されました。
|